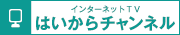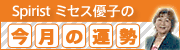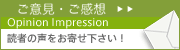アクティブなシニアライフを応援する情報サイト
芸能人インタビュー
- 映像の世界で生きる人間として、今、この瞬間にしか存在しない『リアル』を表現したい。 2012.03.19
-

映像の世界で生きる人間として、
今、この瞬間にしか存在しない『リアル』を表現したい。
一度観たら忘れられない。それほど強烈な個性を持ちながら、
役に入ると『役所広司』という人物はふっと消える。
国内外の映画監督さえ魅了し、観客を自然と物語の中へ
連れて行ってしまう高い演技力は、
新作映画『わが母の記』でも遺憾なく発揮されている。
■答えを探し続ける作業が芝居。その難しさに魅せられる
約束の時間がきた。
広々としたスタジオに、ひげを生やした長身の男性がのそっと現れる。彼は辺りをゆっくりと見回し、取材陣を見つけると黙礼した。椅子に座り、無言のままコーヒーをすする。新作映画について触れると、「観てくださったんですね」と低い声で呟き、かすかに微笑んだ。
話題作の中心にはいつも彼がいる。日本映画界に欠かせない名優だが、「あれで良かったのかな、といつも自分の芝居を振り返る」とポツリ。なんて謙虚な…と思うが、その眼差しは驚くほど真剣だ。
「ワンカットごとに思います。今の芝居で良かっただろうか、もっと別のやり方があったかもしれないと。芝居に答えはなく、監督の『OK』の声だけが頼り。つねに試行錯誤しながら、そのときどきでベストだと思える芝居をしていくしかないんです」
役者として揺るぎない地位を持ちながら、悩むことをやめない。そんな役所さんだからこそ、多くの映画監督が信頼を寄せる。
映画『わが母の記』も、企画の段階で原田眞人監督から声がかかったと言う。
「僕が映画にあまり出ていなかった頃、原田監督の『KAMIKAZE TAXI』(1995年)に出演して、初めて映画づくりの面白さを知りました。それから何度かご一緒させて頂きましたが、今回は10年ぶり。ドキュメンタリータッチを得意とする監督なので、その場に応じて台詞はどんどん変わっていきますし、『このシチュエーションで台詞をつくってください』と言われることもあります。頭の中でイメージしていた芝居が、いざ現場に入ると役に立たない、変えざるを得ないなんてことはしょっちゅう。現場に流れる空気、共演者の個性…そういう“リアル”なものに無意識に反応しているんでしょうね。どんな芝居になっていくのか、自分でもわからないんですよ」
声が熱を帯び始め、次第に言葉数が増える。笑顔がこぼれた。
答えのないものと向き合い、悩み、でもそれが楽しいんだという心の声が聴こえてきそうだ。■役者として譲れないのは、現場でしか生まれないリアリティ
「壁にぶつかってばかりですが、役者を辞めたいと思ったことはないです。他にできることもないし。それに」と、コーヒーに目を落として低く笑う。
「役者の毒ってやつでしょうか。次はもうちょっとうまくできるかも、と期待してしまうんですよ。次こそは、次こそはって毎回。その思いが役者を続ける原動力になっているんでしょうね」
役所さんほど完璧を求める人はそういない。作り手がリアリティを追求するのは当然だが、しかし、それにしても、役所さんの“リアル”へのこだわりようは、目を見張るものがある。「映画には魔術があるんです。たとえ役者の演技力が足りなくても、どうにかなってしまうところがある。映画はシーンを切ったりつないだり、撮影後にいろんな作業を経て完成します。すると現場ではなんとなく不自然だった芝居も、全体で観ると違和感のないものに仕上がる。
だからこそ、僕は現場でのリアリティにこだわりたい。観てくださる人にどこまで伝わるかはわかりませんが、でも、やっぱり、僕は役者だから。演じながら相手と心を通わせ、ぶつかり合い、お互いの“リアル”を引き出して、その場で生まれるナマの感情を大切にしたいんです」
現在、活動の軸は映画だが、役者人生は舞台から始まった。観客は目前、ひとたび幕が開けば最後までひた走る一発勝負。舞台はそのまま“現場”なのだ。そんな世界を知っているからこそ、役所さんは映画での自分に、よりリアリティを求めるのかもしれない。
自らの心と体で、その瞬間にしか存在しない“リアル”を表現する。それは映像の世界で生きる役所さんのプライドなのだ。
「撮影期間中は、プライベートでも役の雰囲気を逃さないようにしています。家族も『あ、また何か連れて帰って来てるな』と感じるようですが、長年のことなのでもう放っておかれています(笑)」■日本の家族愛を描く『わが母の記』…それぞれの母を重ねて
リアリティを追求する役所さんにとって、映画『わが母の記』は真骨頂かもしれない。原作は文豪・井上靖の自伝的小説。撮影は世田谷にある井上の邸宅で行われ、実際の書斎を使用した。昭和の生活感を背景に、個性的な家族の面々が繰り広げる悲喜こもごもの日常を、いきいきと、そして情感豊かに描く。
作家として大成功をおさめ、妻と三人の娘、二人の妹、そして秘書や編集者などに囲まれ、賑やかに忙しく暮らす伊上洪作。しかし幼少期の体験から、伊上は未だに母親を許すことができずにいた。当時の事情により、ひとりだけ家族と離れて育てられたのだ。『僕だけが捨てられたようなものだ』『何言ってんの、兄さん得してるわよ』『そうよ、大変だったんだから』…軽妙な会話劇に圧倒され、観客はいつの間にか物語の中に引き込まれる。
「伊上は軽い口調で、冗談のように『捨てられた』と言うんですが、根は相当深いんです。社会的に成功し、立派な屋敷に住み、家庭を持ち、たくさんのファンもいるのに、心の傷がいつまでも癒えない。きっと書くという行為で精神のバランスを保っていたんでしょうね。作家としての伊上は母を客観的に観察し、優しくもできる。でもひとりの人間に戻ると冷静ではいられない。母が老いて記憶を失い、息子さえ認識できない状態になって、ようやく真正面から向き合えた。ずいぶん遠回りしましたが、それが親子というものなのかもしれない。観る人はそれぞれの『わが母』を重ね合わせるかもしれませんね」
鑑賞後には、温かな涙が頬を伝う。
伊上の複雑な愛憎を見事演じきった役所さんは、「これからも一本一本、真剣に取り組まないといけませんね。たまに、もうこれでいいかなって手を抜きそうになるので…」と、はにかむように笑う。
実はこの日、十数件の取材が詰め込まれていた役所さん。にも関わらず、一つひとつの質問に丁寧に、真剣に応えてくれた。その誠実な姿勢と最後の台詞のギャップが、いかにも役所さんらしい。●役者/役所広司
1956年長崎県生まれ。『KAMIKAZE TAXI』『Shall we ダンス?』『うなぎ』『パコと魔法の絵本』『十三人の刺客』『最後の忠臣蔵』『聯合艦隊司令長官 山本五十六』『キツツキと雨』など出演作多数。日本アカデミー賞最優秀主演男優賞など国内外での受賞歴多数。2009年『ガマの油』で初監督を務める。(C)2012「わが母の記」製作委員会
■映画『わが母の記』
昭和39年。幼少期、兄妹の中でひとりだけ両親と離れて育てられ、「母に捨てられた」という思いを抱えながら生きてきた小説家・伊上洪作。ずっと母と距離を置いてきたが、父が亡くなり、長男である伊上は残された母と否が応でも向き合うことに。伊上の葛藤をよそに、次第に記憶を失っていく母。しかし唯一消えない真実があった…。原作は昭和の文豪・井上靖の自伝的小説。モントリオール世界映画祭で審査員特別グランプリに輝いた感動作。
■ 監督/原田眞人
■ 出演/役所広司、樹木希林、宮崎あおい他■ 4月28日(土)、全国ロードショー