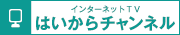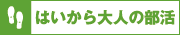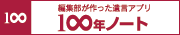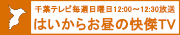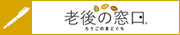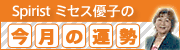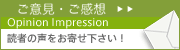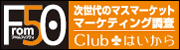アクティブなシニアライフを応援する情報サイト
芸能人インタビュー
- 言葉を受け取る力が求められる今、大切なのはちょっと立ち止まって考えることです 2025.11.17
-
俵万智さんが今年4月に発表した新書『生きる言葉』。“言葉を楽しみたくなる”と大きな反響を呼び、早くもベストセラーに。メールやSNSなど、顔が見えないコミュニケーションが広がる現代。そんな時代に必要な「生きる言葉」についてうかがいました。
多くの読者が共感!
言葉と共にあった子育てエピソード
 社会現象を巻き起こした第一歌集『サラダ記念日』発表以降、歌人として、エッセイも書き活躍する俵万智さん。『生きる言葉』は、日常で使う言葉から、ドラマや短歌、ラップ、SNS、A Iまで、現代の私たちを取り巻く言葉の考察をまとめました。本書は俵さんの子育ての話題から始まります。
社会現象を巻き起こした第一歌集『サラダ記念日』発表以降、歌人として、エッセイも書き活躍する俵万智さん。『生きる言葉』は、日常で使う言葉から、ドラマや短歌、ラップ、SNS、A Iまで、現代の私たちを取り巻く言葉の考察をまとめました。本書は俵さんの子育ての話題から始まります。
「子どもは、まっさらな状態から言葉を段々と覚えて成長します。この本は、縦軸に“子と言葉”というテーマが連なっていて、ある種、子育て本として読んでくださる方が多いようです。自分の子育ては言葉と共にあったことを実感しました」
俵さんの息子は石垣島の全校児童十数名の小学校に通います。違う年齢同士で遊ぶ時、小さい子も混ざれるよう、子どもたちが特別ルールを作って遊んでいたエピソードから、読者から面白い体験がよせられました。
「自分も小さい子を『あぶらっこ』と呼んで遊びに混ぜていた、という感想をいただいたんです。ほかにも、『おみそ』『おまめ』『とうふ』というバリエーションもあって。かつて日本では、同時多発的に小さい子を労わりながら遊ぶルールがあったことを知り、感動しました。ぶつかったり、ちょっと痛い目にあったりしながら、自分たちで遊びのルールを考えるというのはすごく豊かなことだと思うんです。そういう経験を今の子にもしてほしいですよね」三十一音に思いを込める。
短歌を趣味にしてみませんか!
自らを「言葉オタク」と言う俵さん。その独自の視点は、言葉にまつわるもやもやを解きほぐしてくれます。例えば、上の世代が戸惑い眉をひそめがちな若者言葉。最近では、メールなどのやり取りで、文末に句点の「。」がつくと圧力を感じる「マルハラ(マルハラスメント)」や、「○○界隈」などが議論を呼びました。
「若者言葉も現象として観察してみると面白いものです。言葉は生き物ですし、常に変化します。若者なりに使い勝手のいいよう変化させて、色々な言葉が生み出されるのは、健全な状態です。生きている時代が変われば、言葉の感覚も変わるので、言葉を評する時に、間違いか正しいかはあまり言いたくありません。以前、80代の母に『全然大丈夫』と言ったら、『全然はおかしい!』と否定されたのですが、『とても』ならばいい、と言うのです。でも、遡れば『とても食べきれない』や『とてもできない』など、『とても』も否定を伴う言葉だったわけです。自分の感覚だけで闇雲にジャッジしてまうのは危ういと思います」
言葉の力を磨くために、俵さんは短歌を読み、作ることを勧めます。歌舞伎町のホストたちと開いている歌会のエピソードでは、彼らが自分と向き合い、真剣に作った短歌が心に響きます。
「ホスト歌会は、彼らがお客様の心をつかむ言葉や、お客様のちょっとした一言に気づく心を養うのに繋がっていると思います。それは、私たちの日常でも大事な力です。今はSNS時代で発信することに注目されがちですが、同じくらい受け取る力も求められていると思うのです。言葉尻や文字通りの意味だけで、短絡的な反応をしてしまう人が多いですが、ちょっと立ち止まり、その言葉の背景にはどんな思いがあるのだろう、と考えるだけで違う反応ができるはず。言葉を選ぶ作業を日々していると相手の言葉選びにも敏感になれますし、短歌は言葉を発信するのにも受け取るのにも、すごくいいトレーニングになりますよ。私は、読売歌壇で選者をしているのですが、次回までに投稿してみるのはいかがでしょう。自分への宿題として一週間言葉に向き合えば、心の持ち方が変わると思います。五・七・五・七・七だけが決まりです。是非短歌を趣味にしてみませんか!」■プロフィール
歌人/俵 万智
1962年大阪府生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。学生時代に佐佐木幸綱氏の影響を受け、短歌を始める。高校で国語を教えながら作歌を続け、1987年に第1歌集『サラダ記念日』を上梓。280万部のベストセラーとなり社会現象に。翌年、現代歌人協会賞。2023年、秋の褒賞で紫綬褒章を受章。『チョコレート革命』『アボカドの種』『愛する源氏物語』の他、歌集、評伝、エッセイなど著作多数。1996年より読売歌壇選者を務める。
■インフォメーション